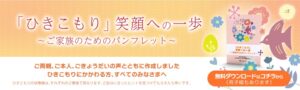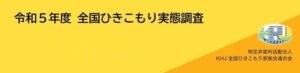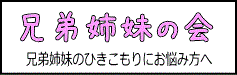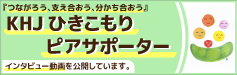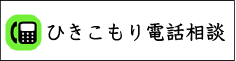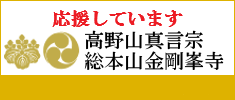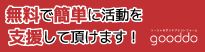KHJ新体制が厚生労働クラブで記者会見
4月18日、KHJ新体制が厚生労働クラブで記者会見を行い、今後のビジョンや厚労省ひきこもり支援ハンドブックへの対応等を表明しました。

まず、東日本大震災の津波でひきこもる次男と妻を亡くし、生前の思いを引き継ぐように『虹っこの家』という居場所を岩手県陸前高田市につくった佐々木善仁共同代表は、「様々な当事者の思いをいろいろな行政機関に話しながら、つなげていきたい。全国の支部の皆さんと一緒に一つ一つやるべきことを解決していければと思う」と話しました。
次に、21年間ひきこもっている息子と暮らしてきた「大阪のおかん」こと日花睦子共同代表は、「家族会とつながるまではどこにも相談に行くところがなく、ひとりで抱えてきた。でも、家族会で皆と話しているうちに私自身が感じている痛みこそ財産なんだと気づいた」「どこにもつながれていない家族たちに“ひとりで悩まなくていいよ”と伝えたくて居場所を運営している」と説明しました。
題佛臣一副代表は、「次女の突然の死によって、考えが変わった。亡くなった子に何をしていたんだろう」と考え、会社を辞めて家族会に入ったことを紹介。「家族会で一緒に考えていける場所があるのはありがたい。全国で悩みを抱えている家族や当事者の受け皿をしっかり作って、ひきこもってる人でも楽しく働けるところもたくさんできるよう皆さんと一緒に考えながら進めていきたい」と抱負を語りました。
また、KHJのビジョンについて、日花共同代表は「親は高齢化して、子のひきこもりが10年、20年と長期化している。待ったなし」の状況であるにもかかわらず、「昨年はニーズを吸い上げられなかった。声は届いていたのに」と反省したうえで、「今年度は支部や地域のニーズを把握し、それに応えるための事業を展開したい。相互の対話を大事にしたい」として、「生きていたいと思えるようになる」ことや「誰もひとりにさせない」という方針を明らかにしました。

さらに、日花共同代表は、1月末に基礎自治体に通知された厚労省ひきこもり支援ハンドブックについても言及。「心が躍ったのは、医療モデルから社会モデルに変わったこと。これまでは自己責任、家族責任と言われ、追いつめられ感があった。希望の持てないまま苦しめられてる家族がたくさんいる」と現状を報告。ハンドブックを活かしていくために、地域や行政との関係づくりをやっていきたい」と表明しました。
以下は、記者との質疑応答。
記者:ハンドブックの理解を広げるための関係づくりをもう少し具体的にお願いできますか?
深谷(本部スタッフ):これまでもKHJでは研修会をしてきましたが、支援の途絶になる理由でとくに顕著なのは、生活困窮。重層的設置のあり方検討会議に当事者が入っていないのはおかしい。市町村間で格差もあります。家族や本人への偏見は今も根強い。いつでも誰でもやり直せる、試行錯誤できる社会を創っていきたいと思っています
日花:ハンドブックには事例がたくさん載っていますので、事実を基に話を聴きたいというニーズが来ています。私たちは、生の声を伝えていくことができます
記者:8050問題や、ひきこもりの現状は、近年どのように変化しているのでしょうか?どんな課題があって、どう活動の中で活かしていくのか、教えてください
日花:家族は疲弊しています。ただ、変わってきたことが感じられるのは事実です。
8年前に自治体に相談したら「ひきこもりなんて、そんな大きな声で言っていいんですか?」と職員から言われ、びっくりしました。隠さなきゃあかんことなのか?と。今ではそういう対応はなくなりました。国が窓口を明確にする取り組みをしてきた結果だと思います。
でも、世間の受け止めや、その中で暮らしている家族、本人の受け止めは、大きくは変わっていません。家族会や居場所への家族の参加は増えてきましたが、当事者にまでは十分届いていないんです。つながっていない。家族の中での本人との関係性が断絶しているのです。追いつめられた感は消えていません。
生きていたいと思えていない。そこに、何とか斬り込めるような家族会の活動にしていきたいと思っています